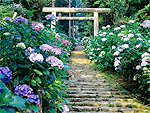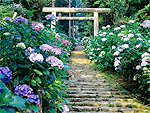|
|
   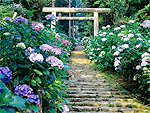 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【 蔵の街 】 栃木県栃木市 |
|
|
舟運で栄えた当時の商家群が残る |
|
|
青々とした柳がゆれる巴波(ウズマ)川は、江戸時代のはじめころから栃木と江戸方面をむすぶ舟運の重要な交通路として賑わった。今でも、江戸時代から明治にかけての繁栄を忍ばせる白壁土蔵、黒壁や格子造りの商家が残る。また、川の中には10万匹の鯉が群泳する。栃木駅から新栃木駅までの約4Kmの遊歩道では、巴波(ウズマ)川や商家をめぐり約3時間で歩ける。 |
|
|
リンク 栃木市 栃木市観光協会 |
|
|
|
|
|
|
【 太平山あじさい坂 】 栃木県栃木市・大平町 |
|
|
アジサイの花につつまれる石畳の階段 |
|
|
6月の大平山は約2000株ものアジサイに彩られる。約1000段ある大平山神社の表参道・石段に沿って色とりどりの花が咲きそろう。雨の日はなんとも言い難い風情。あじさい坂で聞こえる雨蛙の鳴き声は、日本の音百選に選定されている。見頃は6月中旬から7月上旬。 |
|
|
リンク 栃木市 栃木市観光協会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【 三毳山のカタクリ 】 栃木県佐野市 |
|
|
約1.5haが藤紫色、関東最大のカタクリ自生地 |
|
|
三毳山は佐野市の東部に位置し、標高は229m。コナラやクヌギなどの茂る豊かな自然が残る。カタクリ自生地は北部斜面。見頃は、3月中旬から4月上旬。ログハウスのカタクリの里管理センタ−に駐車場があり、シーズン中は観光バスも出入りし賑わう。山頂からは360度の展望が得られる。 |
|
|
リンク 佐野市 佐野市観光協会 |
|
|
|
|
|
|
【 出流原弁天池 】 栃木県佐野市 |
|
|
石灰岩からなる標高150mの磯山山麓、磯山公園の中。石灰岩の地層から湧出した清水が浅く澄んだ周囲138mの池を形成している。湧水量は1日2400t。池の中では鯉などが泳いでいる。池は出流川の水源。全国名水百選。 |
|
|
リンク 佐野市 佐野市観光協会 |
|
|
|
|
|
|
|
【 足利学校 】あしかががっっこう 栃木県足利市 |
|
|
日本最古の総合大学といわれる教育施設の原点 |
|
|
創建については諸説あるが、鎌倉時代初期に足利2代目・義兼が一族の学問所として建てた説が有力。16世紀初頭・天文年間には全国から学徒3千を集め、日本の最高学府だった。儒学を中心に兵学、医学など実用的な学問の授業が行われた。フランシスコ・ザビエルによって海外にも紹介された。1872(明治5)年に廃校となったが、1990(平成2)年に復原された。図書館には国宝も含む多数の古文書が収蔵されている。 |
|
|
リンク ●足利学校 足利市 足利市観光協会 |
|
|
|
|
|
|
【 あしかがフラワーパーク 】 栃木県足利市 |
|
|
野田の九尺藤をはじめ見事な花々の競演 |
|
|
樹齢約140年、1本の藤としては日本一の約500畳の広さがある野田の九尺藤(大藤)で知られる。また、約1.7mもの長い花房をつける大長藤や全長80mの白藤のトンネルなど実に見事。季節毎に8つのテーマをつくり、チューリップやクルメツツジ、バラ、花菖蒲、古代蓮など庭づくりの工夫でより見応えがある。11月中旬から12月はイルミネーションきらめく光の花の庭に。大藤の見頃は4月下旬から5月上旬頃。 |
|
|
リンク ●あしかがフラワーパーク 足利市 足利市観光協会 |
|
|
|
|
|
|
|
【 渡良瀬遊水地 】 栃木県藤岡町 |
|
|
水害対策施設ながら国内屈指の広大な湿原 |
|
|
関東平野の中央で、栃木・群馬・埼玉・茨城の県境に広がる。面積は面積約3300haで湿原としては釧路湿原に次ぐ規模。元々は治水目的に造成された施設だが、現在では絶滅危惧種を含め貴重な動植物の宝庫で、渡り鳥のオアシスにもなっている。約1500haものヨシ原が広がる風景を見渡せ、その影響もあり初夏の早朝には朝霧が発生しやすく幻想的な光景となる。 |
|
|
リンク ●渡良瀬遊水池 藤岡町 |
|
|
|
|
|
|